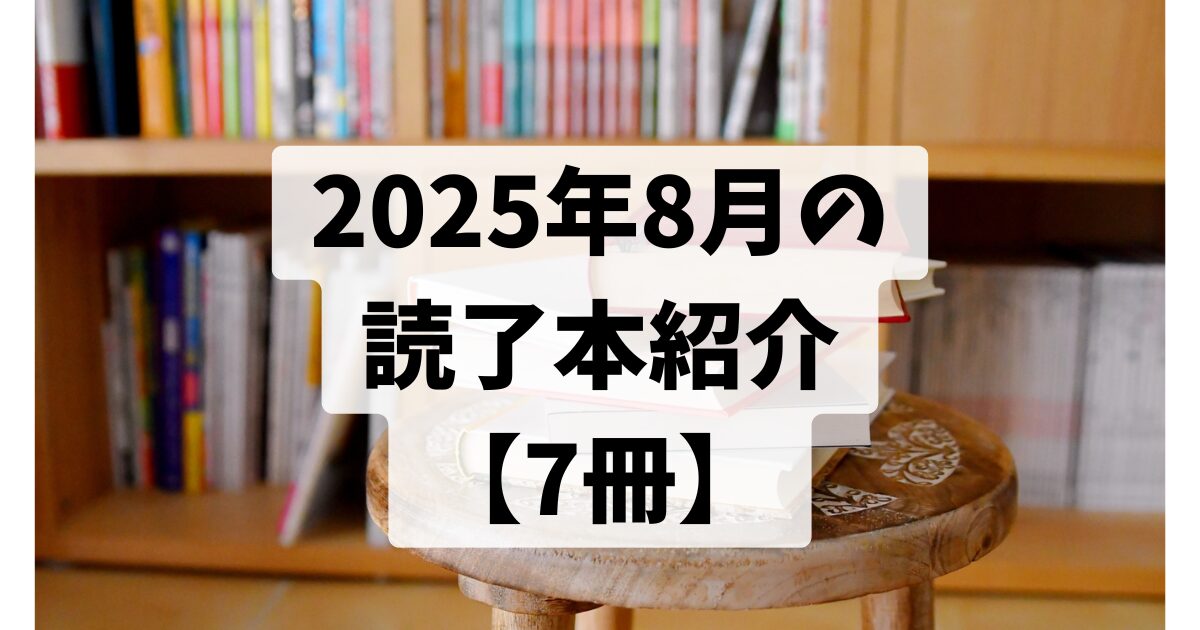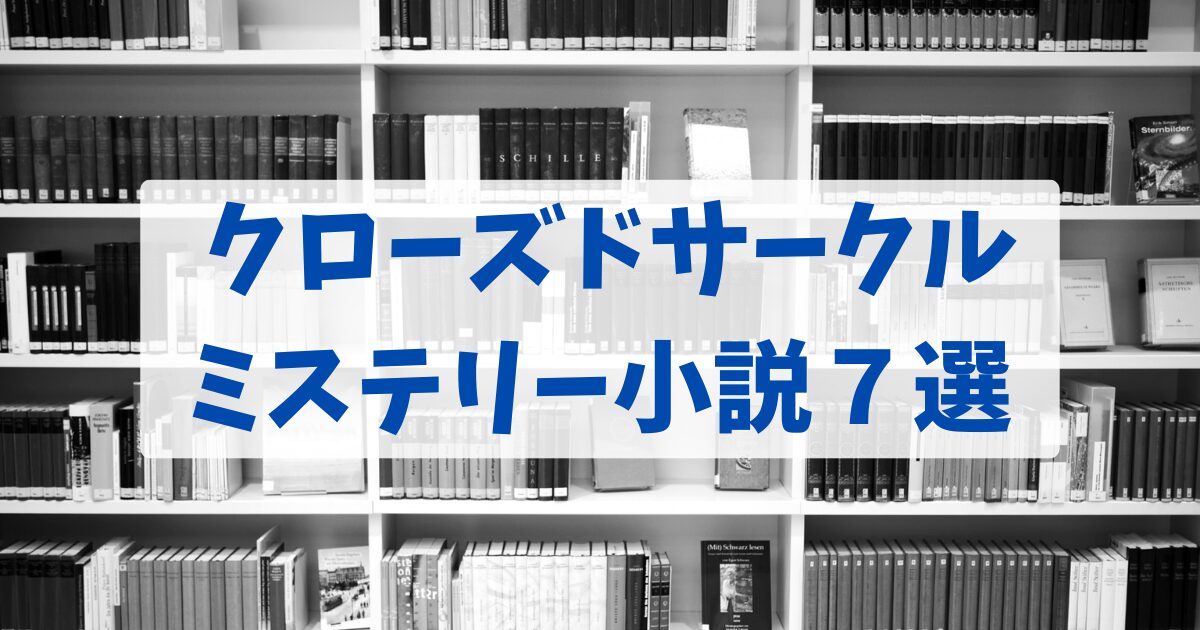名刺代わりの小説10選
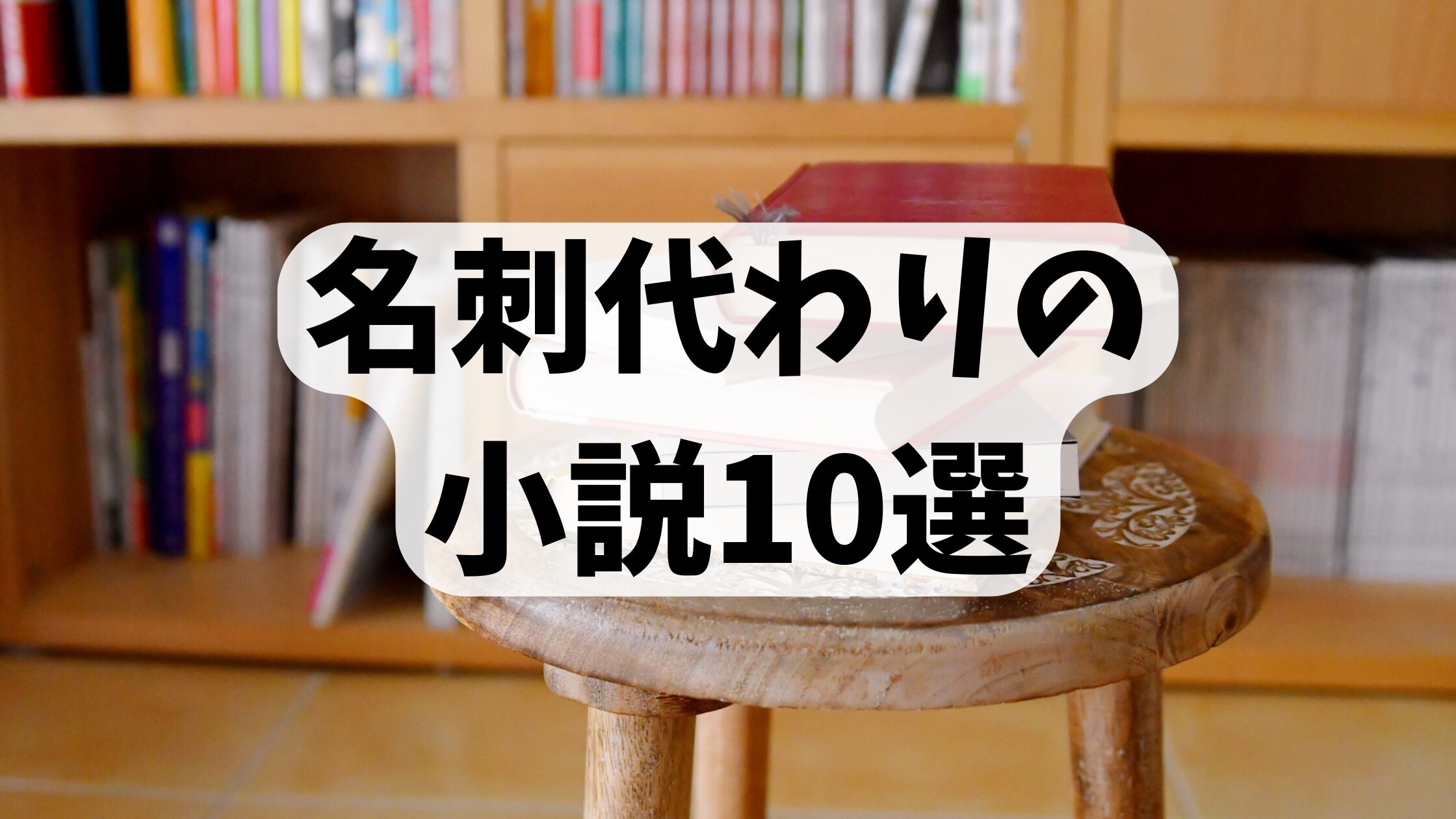
Xの読書垢(読書アカウント)の皆様の間で人気のハッシュタグ「名刺代わりの小説10選」。
読書垢の皆様は、その人の10選のラインナップを見て「この人自分と趣味が似てる」とか、「読んだことない本が入っているけど、この人が選定しているなら面白そう!」とか、いろいろ楽しんでいるに違いありません!
僕もやってみたいなーと思いつつ、読書垢ではないですし固定ポストにしておくのも違うよなー。と思いこれまでやっていませんでした。
でもせっかくの読書好きなので、現時点の小説10選を選定してみました!
やってみて思いましたが、10作に絞るのが難しすぎです。
他にも入れたかった作品はたくさんたくさんありましたが頑張ってみました。
では紹介していきますね!
・ようこそ地球さん/星新一
・宙わたる教室/伊与原新
・火星の人/アンディ・ウィアー 著/小野田和子 訳
・博士の愛した数式/小川洋子
・夜のピクニック/恩田陸
・誰が勇者を殺したか 預言の章/駄犬
・スーツケースの半分は/近藤史恵
・星を継ぐもの/ジェイムズ・P・ホーガン 著/池 央耿 訳
・永遠についての証明 /岩井圭也
・成瀬は天下を取りにいく/宮島未奈

選んでみて思いましたが、自身はバリバリの文系なのにどうやら理系のお話が好きなようです。
理系だったらこんなことを思考できるのかなー、と無意識に憧れがあるのかもしれません。
ちなみに、買った作品もありますが、基本的にはKindle Unlimitedか図書館で借りています。
Kindle Unlimitedなら、月額980円(税込み)で本が読み放題です。
Amazonの読書サブスクサービスです。
月額980円(税込み)で、小説、ビジネス書、漫画等 様々なジャンルの本が読み放題です。
以下ボタンから、Kindle Unlimitedに登録ができます。
初回30日は無料なので、試してみてはいかがでしょうか!
ようこそ地球さん/星新一/新潮社
まずは僕が読書好きとなった原点である、星新一さんのショートショートを紹介させてください。
ショートショートの神様と呼ばれる星新一さん。
偉大すぎてその後のSF作家やショートショートの作家が、「これ星新一作品でみたことある」という読書好きからの指摘に頭を悩ませてしまうくらい偉大です。
星新一作品には中学の頃に出会い、読書の趣味に大きな影響を与え、短編とSF好きになるきっかけを僕に与えてくれました。
正直「星新一作品」として全部を10選に入れたいくらいなのですが、どれか一つに絞るなら本作ですね。1961年に初版が発行されたというから驚きです。
「ボッコちゃん」とも迷いましたが、この「ようこそ地球さん」を選んだ理由は、超有名で実写化もされた「処刑」が収録されているからです。
星新一さんの作品は、ショートショートであるのと話数が多すぎするが故に、題名と内容がしっかり頭に残っている話は少ない、というのが悔しいところです(というか無理)。
でもこの「処刑」は、人類の技術が発展した少し未来で本当にあり得るようなリアリティと、いつ処刑されるかわからない恐怖で、内容が強烈に脳裏に焼き付いています。
星新一作品は、淡々としておりかつ抽象的な表現(具体的に書きすぎない)が多いので、何度読んでも飽きませんし、いつの時代に読んでも通用する普遍的な面白さがあると思います。
書かれた時代を考えるとさすがに若干の古さは感じますが、それを咀嚼しながら読むのも星新一作品のおもしろさだと思います。
ブックオフや古本屋へふらっと行き、びびっときた2-3冊を選び、お出かけの際に持っていく。それが星新一作品の一番の楽しみ方ではないかと思います。
宙わたる教室/伊与原新/文藝春秋
本作は2024年にNHKでドラマ化されたので、ご存知な方も多いのではないでしょうか。
もちろんドラマも観ました。原作が忠実に再現されていて大変面白かったです。
僕にとって、伊与原先生の作品はこの「宙わたる教室」が初めてでした。
きっかけも「Kindle Unlimitedで無料なのでなんとなく目についたから」という程度でした。
結果、序盤からどんどん引き込まれ、一気に読了しました。
本作品を読了後、とにかく伊与原先生の作品なら外れはないはずと考え、「月まで3キロ」、「オオルリ流星群」、「ルカの方舟」、「ブルーネス」などの作品を読みました。
どれもおススメです!
伊与原先生は神戸大学理学部卒業後、東京大学大学院 理学系研究科で地球惑星科学を専攻されたというバリバリの理系。
ですので、本作品のみならず他の作品にも理系要素は満載です。
でも、決して難解だったりつまらなかったりすることはありません。
理系的・科学的な知識や考え方があれば、こんなことができる/考えられるということを教えてくれ、理系の楽しさや面白さを実感させてくれます。
さて、本作品の舞台は定時制高校。
不登校だったり、勉強があまり得意でなかったり、家庭の事情があったりといった若年の生徒に加え、社会人や年配の方等も生徒として通っており、いわゆる全日制の高校とは雰囲気が異なります。
ですので、定時制高校に少しネガティブなイメージを持たれている方も多いと思います。
そんな定時制高校に作られた「科学部」で行われる火星の実験。
しかも実話をもとにしたストーリーというからさらに驚きです。
各登場人物の過去やコンプレックスが紹介され、ときに衝突し苦しみながらも少しずつ前向きになっていき、とある目標に向かう。
クラス担任であり科学部顧問の藤竹先生のよき指導者っぷりが素晴らしい。
個人個人の優れたところや個性を客観的かつ公正に見極め、生徒が一丸となって進むよう寄り添ってくれるし、躓きそうなときには生徒に気づかせるように手を差し伸べてくれる。
たかが定時制高校の科学部と侮ることなかれ。実験の内容はとても有用でかつ独創的です。
生徒が目標に向かって頑張る姿に感動するのは上記のとおりです。
加えて、科学の実験ってこんな感じで役割分担し、仮設を立てて検証し、再現性を高めていくんだな、というプロセスも実感できます。
こんな先生がいたらたくさんの迷える若者たちの人生が好転するかもしれない。
本気でそう思わせてくれます。
僕自身は数学がどうしても好きになれず文系を選択しましたが、藤竹先生のような方にあっていれば、僕の人生も変わっていたかもしれません。
作中には、後ほどご紹介する「火星の人」、「星を継ぐもの」というSF小説も登場します。「宙わたる教室」のNHKドラマ放送中、火星探査機:オポチュニティが話題になったのも記憶に新しいですね。
そして、俺たちの教室は今、宇宙をわたる。
本作のタイトルのベースとなったこの一文。最高です。
火星の人/アンディ・ウィアー 著/小野田和子 訳/ハヤカワ文庫SF
上の「宙わたる教室」にも登場したハードSFの傑作「火星の人」。
本作は現代より少しだけ未来のお話です。
有人火星調査のため火星へ行ったワトニー一行。
しかし、猛烈な嵐のため任務の途中で急遽地球への帰還を余儀なくされました。
そんな中、主人公であるワトニーに暴風で折れたアンテナが直撃。
他のメンバーは彼が死んだものと判断し、彼を火星に残したまま帰還してしまいます。
ところが、ワトニーは奇跡的に生存していました。
しかし、火星に独りぼっちで酸素も食料も限りがある。
彼以外は彼を死んだものと認識している。地球との満足な連絡手段もない。
たった1人で残されてしまったエンジニア兼植物学者のワトニー。
火星のハブ内でのジャガイモの栽培に成功するも吹き飛ばされたり、地球との通信手段がなくなったりと、まさに「致命的」なトラブルに見舞われながらも、自分の知識と限られた物資で生存と脱出をめざすハードSFです。
火星人が出てくるわけでもワープのような超化学的な描写もない。
SF(サイエンスフィクション)だけど、本作品中に描写されているのは現代よりちょっとだけ進んだ技術と一般的な化学知識・法則のみ。
誰も火星には行ったことがない。
でも「もし火星に取り残されたらこうなるんだろうな」と読者に疑似体験させるような、リアルなSFです。
絶望的な状況でありながらも、ワトニーは決して諦めない不屈の精神と持ち前のユーモアで火星からの帰還を目指します。
そんな彼のひたむきさ、そして彼一人を救うために全世界の人々が一丸となる展開に胸が熱くなります。
最後は泣きました。もはや言葉は不要です。
ちなみに、本作品はハリウッドで「オデッセイ」として映画化されており、そちらのクオリティも大変すばらしいです。
特に、どうしても小説ではわかりにくい部分を映像で補完できるので、小説を読んでイマイチ理解ができなかった方にもおススメです。
でも、ぜひ小説を読んでいただきたいです。
映画ではどうしても尺の問題で省略や簡素化されている部分があり、原作読者には若干物足りなさが感じられてしまうからです。
モーニングで連載中の漫画:宇宙兄弟(小山宙哉/講談社)が好きな人はこの作品も好きと断言できます!
逆に「火星の人」が好きで「宇宙兄弟」を未読の方はぜひ読んでいただきたいです。
博士の愛した数式/小川洋子/新潮文庫
この作品も2006年に映画化されていますね。
僕はまだ視聴していないのでいつか観たいです!
ある時点で記憶の更新がストップしてしまい、80分しか記憶が続かない「博士」と、その家政婦である主人公、と主人公の息子であるルート(√)。
この博士の家に来た家政婦は、何人も続けてすぐに辞めてしまっていました。
博士は80分間しか記憶が続かないため、その度に気難しい初老の博士に一から説明をせねばならず、また度々挟まれる数学の話にうんざりするからです。
主人公もその1人。最初は博士の家政婦として働くことに苦戦していました。
しかしあるとき、不意に数学の美しさに気づき、博士のことを少しずつ理解するようになります。
また、シングルマザーである主人公は、あるときから息子を博士の家に連れて行くようになります。
子供好きの博士は彼をとても気に入り、彼の平らな頭から連想した数学記号である「ルート(√)」と名付けます。
博士と親子2人の、奇妙だけどどこか温かな物語。
数学とそれを愛する博士の説明の美しさ、分かりあえても記憶が失われてしまう切なさ。
変わらない博士と、博士に触れることで変わっていく親子。
何も起こらない穏やかなストーリーに心が洗われ、記憶が80分しかもたないはずなのに、徐々に博士と親子2人の心は通い合って親密になっていくような感覚にさせてくれます。
作中には数学がよく出てきますが、数学なんて知らなくても読める。
というより、数学が苦手という方にぜひ読んでいただきたいです。
読みながら計算なんてする必要はありません。
博士による熱のこもった解説と、一見無機質に見える数字や数学用語が持つ数々の魅力で、初めて「数学が美しい」という感覚を理解させてくれます。
最後まで読んで、「親子2人が博士と出会えてよかったな」と本気で思うことができる。
そんな小説です。
夜のピクニック/恩田陸/新潮文庫
夜を徹し、ただ歩き、友と話す。
ただそれだけのことなのに、なぜこんなにも心の深くにすっと入ってきて、じんわりとあたたかい気持ちにさせてくれるのか。
2004年に出版されてから早20年以上の年月が経ちましたが、今後も語り継がれるだろう名作だと思います。
本作品の主人公の融(とおる)と貴子(たかこ)が通う北高には修学旅行がなく、その代わりに、全校生徒が夜を徹して80キロを歩き通す「歩行祭」という伝統的な行事が存在します。
同じクラスの同級生である融と貴子ですが、とある事情から2人は会話をしません。
そんな貴子には、この「歩行祭」を通して達成したい一つの目標がありました。
「歩行祭」はその名のとおりただただ歩くだけ。
チェックポイントを通過し、途中で休憩し、足の痛みを会話でごまかしながら。ただ歩く。
何でもない、ただ友と歩くだけの時間が、大人になってしまった今となっては何よりもかけがえのない貴重な時間と気づかせてくれます。
その時には当たり前に立ち入ることができた場所、学校に行けばいつでも会えた友人たち。もうその場所やその人への元へは、僕らは戻れません。
家庭の事情とか、部活とか、友情とか、しがらみとか、男女の恋愛とか、進学への不安とか。
高校生特有の甘酸っぱい、でもその時を生きている本人たちにとっては何より大事なもの。でもすべてがうまくいくわけもなく、もどかしい。
僕らが高校時代に置いてきたそんなふわふわした感情を呼び起こしてくれるような、素晴らしい小説です。
高校が楽しかった人もそうでない人も、何かに打ち込んだ人もそうでない人も。
この本の中には、誰もが共感できるシーンが必ずあるはずだと感じます。
「歩行祭が終わって朝を迎えたら、何かが変わっているんだろうな。」
登場人物たちが思っているであろうそんな感覚を、読者も物語のゴールに向かうにつれ疑似的に感じることができます。
貴子の目標は叶ったのでしょうか?叶ったら何か変わるのでしょうか。
読んでみたら、わかります。
誰が勇者を殺したか 預言の章/駄犬/角川スニーカー文庫
まさかのライトノベル(いわゆるラノベ)が10選入り!
それくらい僕にはハマる作品でした。
僕はこの「誰が勇者を殺したか」シリーズで、中学生以来久しぶりにラノベを購入しました。
ちなみに僕が当時読んでいたのは「フルメタル・パニック!」「魔術師オーフェン」「デュアン・サーク」などなどです。あー懐かしい。
挿絵が入っていることに懐かしさを感じながら読みましたが、まさに僕と同世代のRPG好きは読んでみて後悔の無い作品です。
この「誰が勇者を殺したか」シリーズは、本記事作成段階で以下の3作が出版されていまして「預言の章」はシリーズ2作目です。
・1作目:誰が勇者を殺したか
・2作目:誰が勇者を殺したか 預言の章
・3作目:誰が勇者を殺したか 勇者の章
本作品を紹介する前に、一作目である「誰が勇者を殺したか」を簡単に紹介させてください。
【前作のあらすじ】
魔王を倒す勇者の元には、預言者が姿を現すという。
その預言を受けた勇者は魔王を倒し、帰らぬ人となった。
そんな勇者の偉業を文献として編纂すべく勇者の仲間に話を聞くが、どうも要領を得ない。
勇者と仲間の過去を遡りながら、次第に真相が明らかになっていく。
勇者がいかにして勇者となり、仲間と出会い、死んだのか。
――誰が勇者を殺したか。
1作目でとてもきれいに完結したため、2作目である本作品はどのような内容になっているのかとワクワクして読み進めました。
結論、前作を補完しながらもよりRPG好きのツボを押さえた内容で、めちゃくちゃ面白かったです!
前作を未読の方はまずそちらを読んでくださいね。
この2作目は、勇者とは程遠い金目当ての冒険者「レナード」とその仲間の冒険を、預言者視点で追いかけた内容となっています。
最初はレナードの言動に辟易していた預言者ですが、彼らの言動を観察するうちに、徐々に彼らも魔王を倒しうる「勇者」なのではないかと思うようになります。
本作品にも前作同様、RPG好きにはたまらないポイントを盛り込まれています。
・一度世界を救い、頼りになるサブキャラとして登場する前作の主人公たちの扱い
・前作のその後が垣間見えるが、想像の余地を残してくれる「クリア後」の世界
・読者は「影の功労者」を知っていて、作中でその評価が追い付いてくる展開
等々、あげればキリはありません。
前作も本作品も、一見「ベタ」なように感じるんですけど、そのベタな展開ってどこで見たの?と聞かれても答えられない。
RPG好きの僕らの頭の中にある「ベタ」がうまく体現されたような感覚を持ちました。
主人公は生まれながらの勇者ではない。勝ち残ったものが勇者になる。
RPGをプレイしていると感じる違和感に一つの解釈を与えてくれた。そんな作品です。
「ライトノベルは若者向きだから今更読まない」と敬遠せず、一度読んでみてはいかがでしょうか?
――誰が勇者を殺したか。
スーツケースの半分は/近藤史恵/祥伝社
世界を旅するブロガーを目指す僕としては、ずーっと読みかった本。
図書館で発見したときはテンションが上がりました。
物語の舞台は現代の日本。
兼業主婦として働く女性:真美は、フリーマーケットで見つけた素敵な青いスーツケースに一目惚れし購入します。そして真美はそのスーツケースをもって憧れのNYへの一人旅を決行します。
本作品は短編集で毎回主人公が変わります。
真美の次は友人が、その次はまた別の友人が、といった形で青いスーツケースは順番に世界中を旅します。
一編が終わると、その旅の後に別の誰かが旅に出るところから次の編が始まるのですが、次は誰とどこを旅するんだろうと編ごとにワクワクさせてくれます。
話が進むごとに、それまでの編の後日談が描写されているのも嬉しいですね。
本作品では、大きな事件も悲しい出来事も起こりません。
スーツケースとともに旅をして、体験をして、自分と世界を知って、帰ってくる。
疲れているときやちょっとメンタルが落ち込み気味なときって、暴力的だったりハラハラしたりする作品ってなかなか読む気がおきません。
そんなとき、この作品のような穏やかな本が手元にいくつかあれば、安らぎを与えてくれる気がします。
本作品には順番に旅をする各編の主人公たちに加え、いろんな人物が登場します。
旅に不馴れな人、旅慣れた人。既婚者、独身。留学する人、夢を追う人。…etc。
それぞれ、いろいろな思いや夢がある。
一見何のストレスがない人にも、焦燥感だったり変えたい現状があったりする。
旅はそんな自分を変えるきっかけをくれる。のかもしれない。
旅をすると、スーツケースが汚れたり傷ついたりする。
その度に、思い出や経験が増える。そんな感覚を擬似体験させてくれるような一冊です。
旅なんて、いってみたらどうにかなる。
何かトラブルがあっても後で笑い話になりますし、行くか迷っているなら早めに行くべきと思います。
正直、想像以上にめちゃくちゃ好みでした!
「旅がしたい」そう思ったということはいくべきなんでしょう、どこかに。
「あなたの旅に、幸多かれ」
星を継ぐもの/ジェイムズ・P・ホーガン 著/池 央耿 訳/創元SF文庫
海外SF作品をもう一作。
こちらも上で紹介した「宙わたる教室」に作品名が出てきましたね。
ということは名作です。間違いありません。
先に紹介した「火星の人」がリアル路線を追求したハードSFだとすると、本作品は「こんなことはあり得ないけど、これが事実なのでは」と本気で思わせてくれる、想像力に富んだ内容のSFです。
本を開くともう最初から謎。月で発見された5万年前の人類ってなに?
それだけで本作を読む意欲を駆り立ててくれます。
その後も、月で発見された人類である「チャーリー」の所持品や、新たな手掛かり、追加情報により進む解明と、その度にさらに深まる謎。
各分野の専門家が数多くの謎を科学的かつ論理的に紐解いていく過程がとても面白いです。
研究者ってこんな感じに検証+考察し、仮設が事実であると推測していくのかと、作品に関係していないところでなぜか感心してしまいました。
月での「チャーリー」の発見をきっかけに、我々人類の誕生のルーツまで紐解かれます。
オーパーツって実はこうやって残されるんだなとか、現代の技術でも解明されていない謎の真実はこれだったのか、といったように、実際の世界で謎とされているものに対し、どんな真実でもあり得るんだろうな、とロマンを感じさせてくれるような作品でした。
最後もまたいい。
「それ」があれば、推論が事実に変わるんだ!と裏付ける証拠はある。
でも「それ」は、必ずしも有識者には発見されず、人知れず埋もれていく。
その儚さが、読者に心地よい余韻と真実を知っているんだという優越感を与えてくれます。
現在の常識。それは真実ではないかもしれません。
文句無しの傑作SFです!!
永遠についての証明 /岩井圭也/角川文庫
第9回野性時代フロンティア文学賞受賞作。
岩井圭也先生のデビュー作というから驚き。マジでこれデビュー作ってどういうことだ・・

すみません。読んだのがかなり前なので細部はうろ覚えです。
いつか再読しレビューします。とにかく面白かったです。
本作は「数学」に魅入られた数学者たちのお話。
「コラッツ予想」という実在する数学の未解決問題をテーマにしています。
「数覚」に恵まれた三ツ矢瞭司は、天才であるが故に理解者が現れず、徐々に孤独になり命を落としてしまいます。
天才は常人には理解されないものであると思いますが、天才が理解されず嫉妬され虐げられていく様がなんとも具体的で、読んているこちらがもどかしくて心を痛めてしまいます。
自身も類まれなる数学の才能を持ちながらも、自身をはるかにしのぐ天才である瞭司を友人にもつ熊沢勇一は、そんな瞭司と共に切磋琢磨しながらも、同時に嫉妬を覚えてしまいます。
そして、ともに数学を愛する友人たちは別々の道へ歩み出してしまいます。
「天才」は、多分地位とか名誉とか肩書とかそんなモノは関係なしに、自分のしたいことを追求したいだけ。でも、追求しようとするとどこかに所属して誰かと関わって、誰かのためになることもしないといけない。
研究者が抱えてしまうジレンマを痛いほどに感じてしまう小説でした。
そんな天才:瞭司が未完のまま残してしまった超難問「コラッツ予想」。
成長した熊沢は、瞭司が残した研究ノートと共にその証明に挑みます。
スポーツとは正反対のように思える数学の証明。それでこんなにも熱い展開にできることに感動しました。
学生時代の友情と葛藤、研究者としての立場と友人への思いに揺れる心、それらのもどかしい思いを感じながら物語は進みます。
最終盤の二時間にも及ぶ特別講演での証明のシーンは圧巻。
最後の一行を書き終え、「以上です」までの空白の時間を
“大きく上がった打球がスタンドに入るのを見守るような緊張感”という表現が、それしかない描写だし最高に好みです。
本作は、「博士の愛した数式」と同様に、数学なんて全くわからなくても楽しめます。
むしろ数学が苦手だからこそ「数学ってこんなに美しいんだ」と感じることができ、同時に、数学に魅せられる人の気持ちが少しだけ理解できる気がします。
今ならKindle Unlimitedで0円で読めます。チャンスです。
成瀬は天下を取りにいく/宮島未奈/新潮社
通称、成天(なるてん)。
宮島未奈先生のデビュー作にして、「2024年本屋大賞」や「坪田譲治文学賞」、「キノベス!2024」等々、数々の文学賞を総ナメにした作品です。
※なぜかこの本を読むと、「成瀬あかり」とフルネームで呼びたくなります。僕だけでしょうか。
島崎、わたしはこの夏を西武に捧げようと思う
本作品を読み始めて最初に出会う上のこの一文がとにかく好きで、この時点でぐっと引き込まれました。
表紙にプロ野球チームの西武ライオンズのユニフォームを着た主人公:成瀬あかりが描かれていたり、成瀬あかりが上記のセリフを言ったりしてるからって、本作品には野球はほぼ関係ありません。
滋賀県に住む中学生の成瀬あかりは、コロナ禍で閉店を控える地元の西武大津店に毎日西武ライオンズのユニフォームを着て通い、何とか閉店を阻止しようと企みます。
他にも、いきなり丸刈りにしてみたりM-1グランプリを目指してみたり。
周囲からは浮いてしまいがちな行動も、彼女の信念の強さと実際に実行してしまう行動力のおかげで貫き通してしまいます。
とにかく成瀬あかりは天下を取りにいく。
自分が気になったこと、目指したことはなんでもやってみます。
そんな成瀬を見る第三者目線で物語は進むのですが、客観的だからこそ彼女の芯の強さとひた向きさがとても伝わってきます。
そんな成瀬あかりと周囲のバランスをとってくれて、かつ成瀬のよき相方(実際にM-1予選も漫才の相方となります)である同級生:島崎みゆきもとてもいいキャラ。
成瀬あかりより島崎の方が好きになったという方も多いのではないでしょうか。
確かに彼女は難関大学を目指すほど賢く、周囲の視線を気にせず自分のやりたいことをやる行動力も持っています。
この本を読むと、一見「彼女が特別に優秀だから天下を取りにいくことができるのであって、自分なんてとても真似できない」と錯覚しそうになります。
でも成瀬あかりの言動をよく見てみると、叶えたいことをとにかくやってみて一個でも叶えるために動いて確かめる。というポリシーに従っているだけ。
「年齢も性別も関係ない。自分もまだ何かを始めるには遅くない!」とポジティブに思わせてくれますね。
特に事件が起きたり謎があったりしない、SF要素もなければ、ベタベタな恋愛要素もない。
滋賀県を舞台に普通(というには少し変わっているけど)の少女とその周りの人の物語が進むだけ。
いったい何がそこまで読者を、彼女とこの作品に惹き付けるのか。考えてもわからない。
一つだけ言えるのは、読んだらみんな成瀬あかりのファンになる。それだけですね。
本作の続編である「成瀬は信じた道をいく」 通称:成信(なるしん)も発売中です。
大学生になって行動範囲も広がった成瀬あかりと再会できます。
彼女のファンになった方はぜひ読んでみては。
以上、名刺代わりの小説10選でした!
選ぶのに大変悩みました・・・
もちろん個人の好みによりますが、どれも名作揃いです!
是非読んでみてください。
おわり
本を読んだ感想でポイ活ができる「ブクスタ!」についてはこちらの記事をご参照ください。
バナーから新規登録できます!
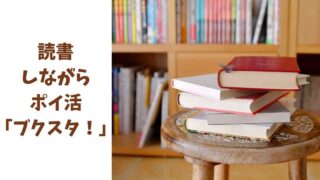

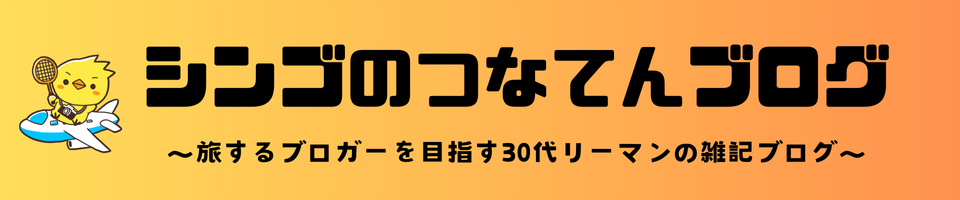
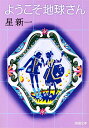










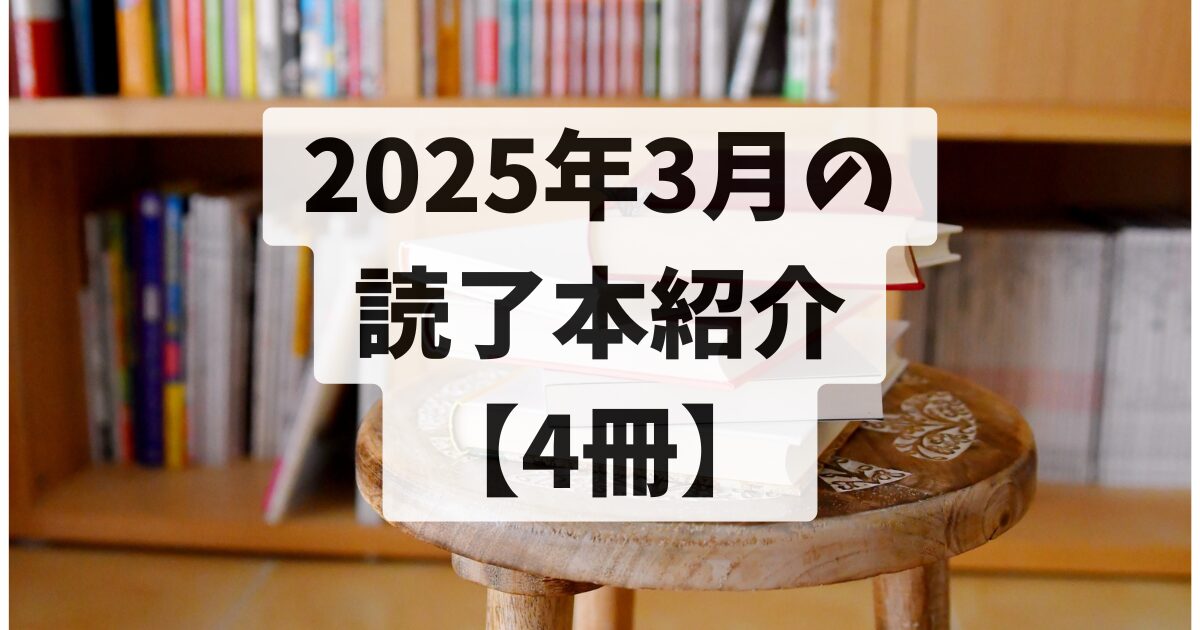
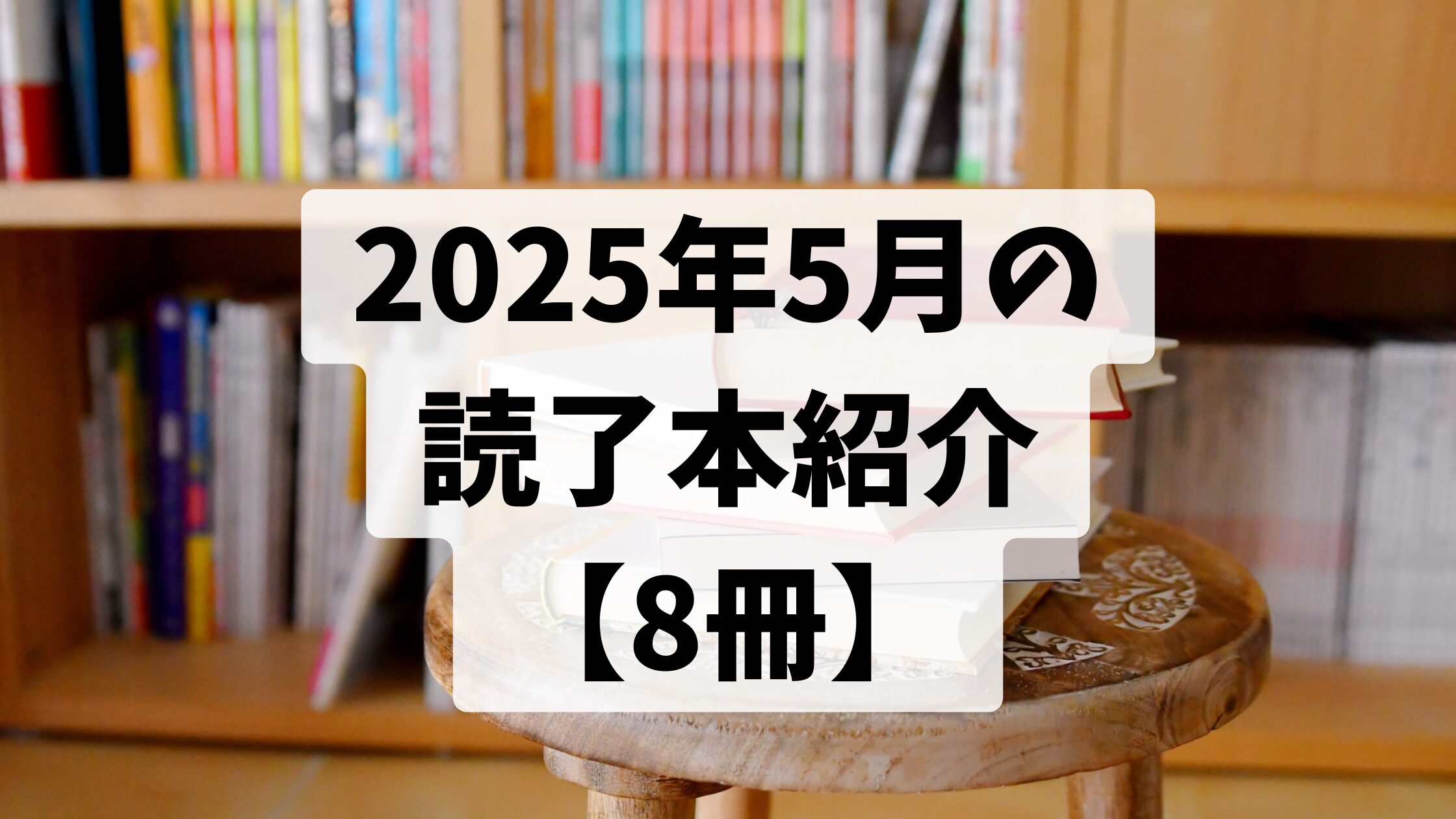
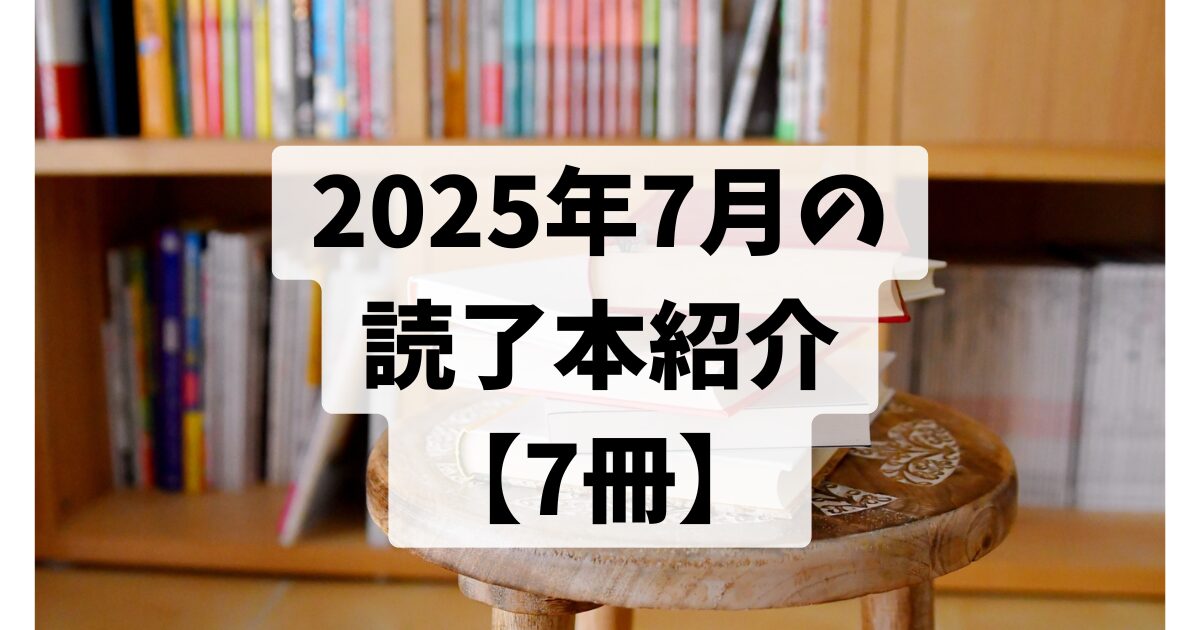
![読書しながらポイ活 [ブクスタ!]](https://shingonotsunaten.com/wp-content/uploads/2024/12/333c4b175564b1695616e8bda3a60528.jpg)