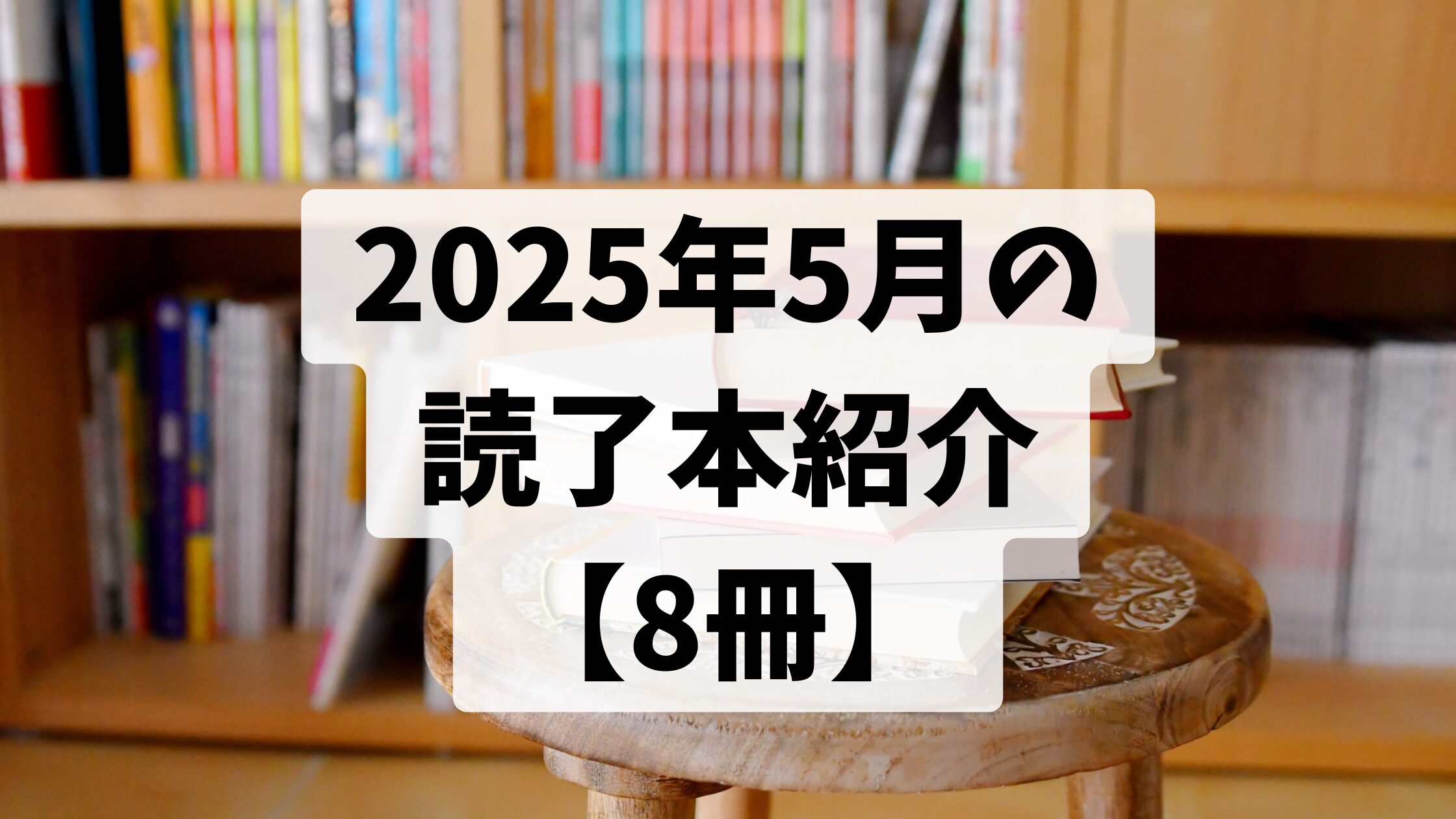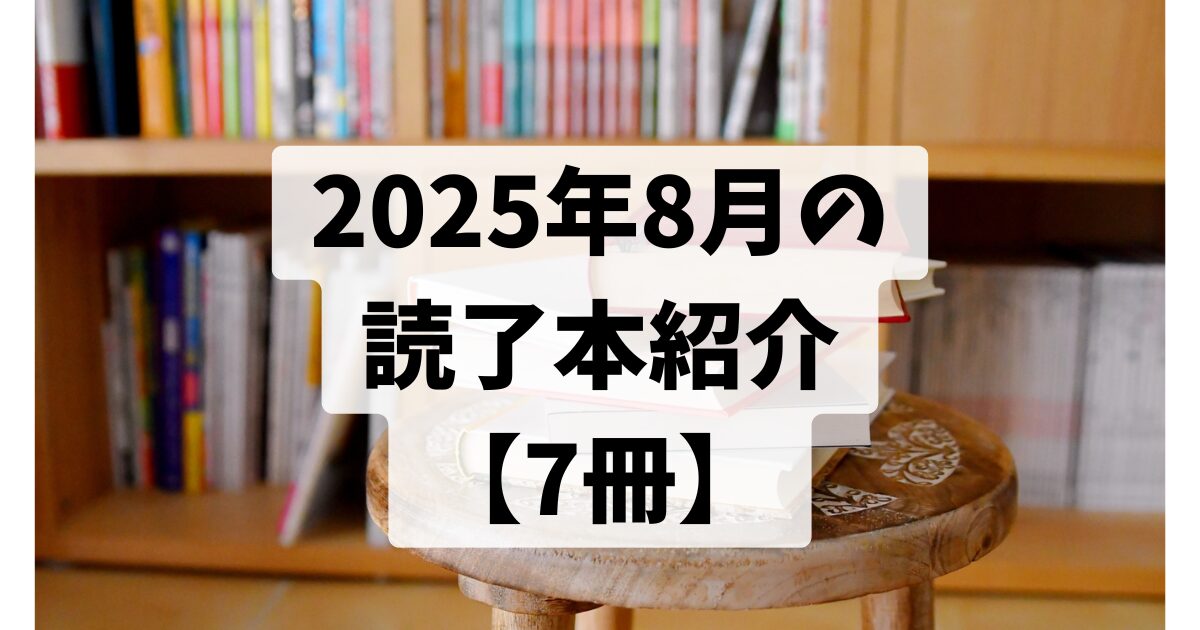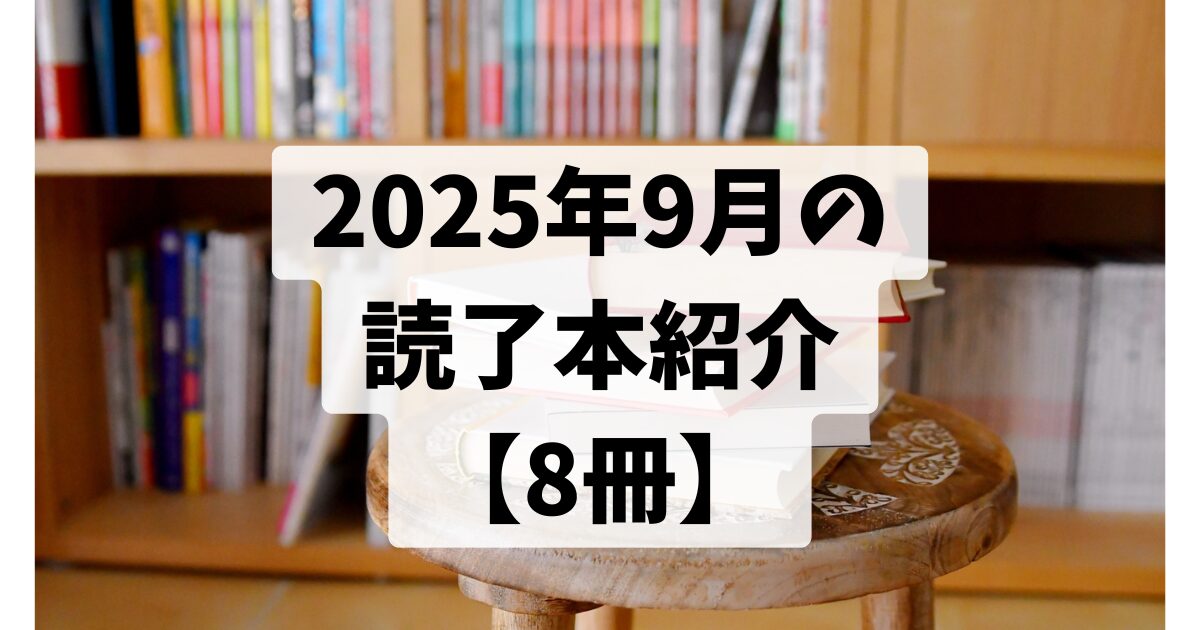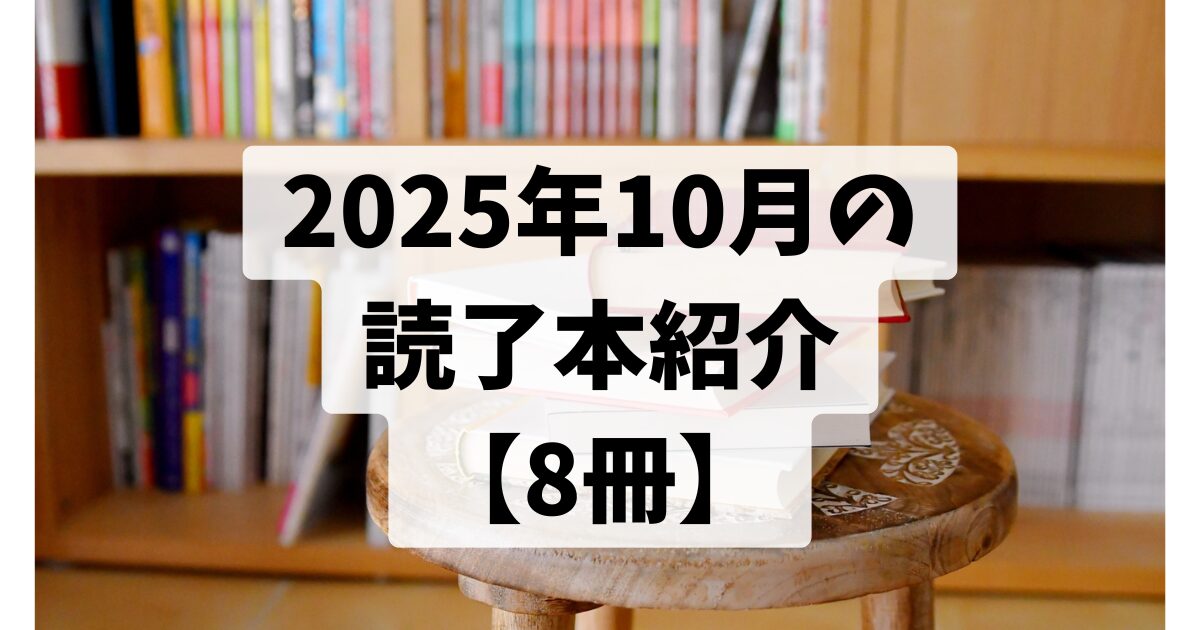2025年上半期のベスト10冊
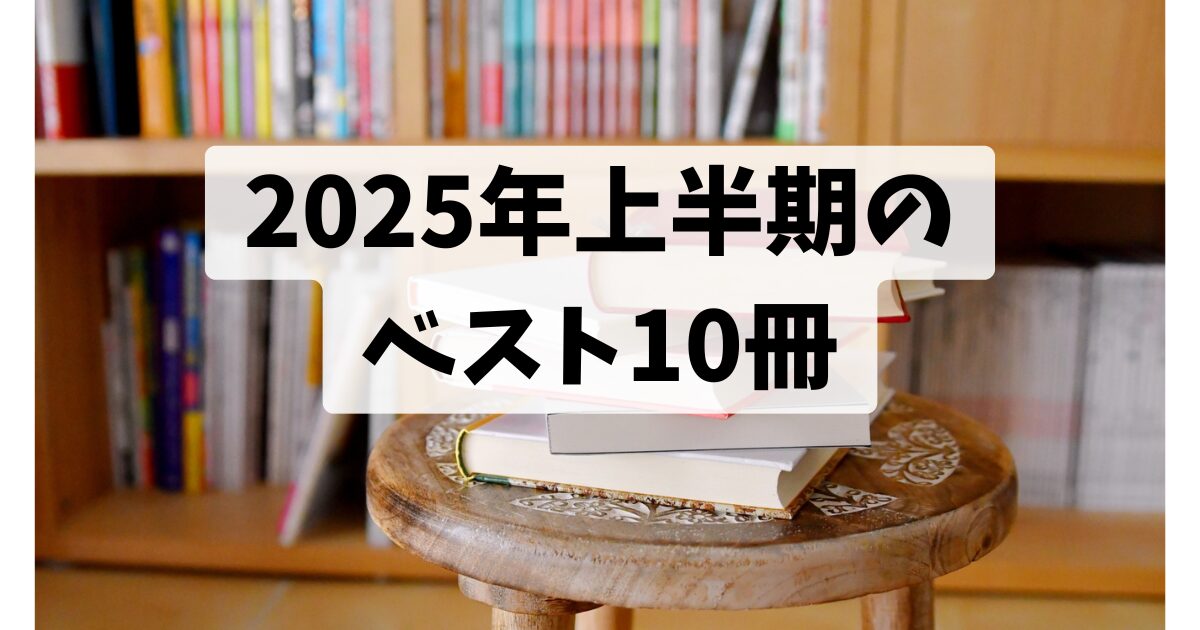
2025年もあっという間に半年が経過しましたね!
2025年1-6月は合計40冊を読みました。
転勤+引っ越しの準備や手続きでバタバタだったためあまり数を読めない月も多かったですが、半年間で読んだ40冊の中から個人的ベスト10冊の本を紹介します。
こうしてまとめてみると、図書館で借りた本も多いですね。図書館サイコー!

ネタバレはありませんので安心してお読みください!
作中からの引用部分は青字にしています。
「ブクスタ!」なら趣味の読書をしながらポイ活でお小遣い稼ぎができちゃいます!
下のバターから新規登録できますので、ぜひ試してみてください。

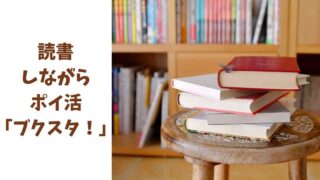
①同志少女よ敵を撃て/逢坂冬馬
②アルプス席の母/早見和真
③アリアドネの声/井上真偽
④ゴリラ裁判の日/須藤古都離
⑤ジェリーフィッシュは凍らない/市川憂人
⑥そして誰もいなくなった/アガサ・クリスティー
⑦十角館の殺人/綾辻行人
⑧がんになってわかったお金と人生の本質/山崎元
⑨どこでもいいからどこかへ行きたい/pha
⑩誰が勇者を殺したか 勇者の章/駄犬
同志少女よ、敵を撃て/逢坂冬馬/早川書房
図書館より貸出
第11回アガサ・クリスティー賞受賞作。
普段、戦争系の小説はあまり手に取らないのですが、X(旧Twitter)で読了記録をよく見かけるので読んでみました。
結論、すごい小説を読みました。これがデビュー作というから衝撃です。
この本を書くためにどれほどの勉強と下調べをしたのかと思うと気が遠くなりますね・・・
時は第二次世界大戦真っ最中のソヴィエト連邦。
農村に暮らし、外交官を夢見る聡明な少女:セラフィマは、ドイツ軍によって村を焼かれ、ただ一人生き残ります。
そこへ現れたソ連赤軍の女性兵士:イリーナによりセラフィマは救われるのですが、セラフィマは他の少女たちと共に女性狙撃兵になるための訓練兵となります。
セラフィマは、自身の母親を殺した敵の狙撃兵、そして村人たちを侮辱したイリーナを殺すため、狙撃兵として戦うことを決意し、成長していくという物語です。
この作品が発行されたのは2021年11月。
その数か月後の2022年2月に、ロシアによるウクライナ侵攻が始まります。
第二次世界大戦終了後は永遠に続くと思われたロシアとウクライナの深い友情。
それが瓦解した世界情勢もあって、本作品はより一層注目されたのではと考えます。
狙撃兵となるための訓練兵時代、狙撃兵に必要な知識やスキルに加え、狙撃兵として持つべきマインド等が非常に丁寧に描写されており、とても面白かったです。
狙撃兵は敵を撃つだけでなく、戦況を鷹の目のように見ることがとても重要な役割であることについて具体的なシーンともに描写をされていましたし、歩兵と狙撃兵が相いれない理由についても、とても分かりやすくて腹落ちしました。
また、セラフィマ達が実戦に駆り出されてからはとにかく辛い描写の連続でした。
戦闘で壊されていく街と殺されていく市民や仲間。戦地で遊ぶ子供たち。
生き残る度に高まる練度と、戦争が終わった後には必要のないスキルや麻痺する感情。
戦争の悲哀、永遠ではない平和、戦争の中の女性、あり得た別の未来。戦後を生きなければならない兵士たち。
彼はサッカー選手だったかもしれないし、彼女は外交官だったかもしれない。
動機を正当化して戦争を始め、行動をまた正当化する。
誰も彼もが「自分の行いは正しいものだ」と自分で自分を麻痺させる。
最も印象に残ったのは、ネジ職人の話です。
ただ、彼/彼女は人よりネジを作るのが、銃を撃つのが上手だっただけ。
それだけで持ち上げられ、尊敬される。
彼ら/彼女らは、自身と家族の平和しか望んでいないのに、世間が、仲間がそれを許してくれない。だから彼らはその役割を全うしなければならない。
「敵」とは誰か。
戦争の相手国か、親を侮辱した仲間か、女性を虐げる男性か、はたまた戦争を指示している母国の長か。
主人公だけでない、女性狙撃兵たちが自身の「敵」を撃つために戦う。
ぜひ一度読んでみてほしいです。
アルプス席の母/早見和真/小学館
図書館より貸出
2025年本屋大賞 第2位の作品。
本当は女の子のお母さんになりたかった
こんな一文からはじまる、野球少年を息子に持つシングルマザーが主人公のお話。
まず表紙がいいですね。
阪神甲子園球場の一塁側アルプス席から、保護者お揃いのピンクのチームTシャツを着てチームと我が子のプレイを祈るように観る母親。
この物語は、高校球児を息子に持つ母親という珍しい設定の小説です。
主人公:菜々子は旦那を失くし、女手一つで息子の航太郎を育てます。
彼女は野球に全く興味はないけれど、息子にはとても素晴らしい野球の才能があって、中学まで大活躍。
関東に暮らすこの親子は、大阪の高校への進学を決めます。
そんな高校での野球部の生活、そして保護者会の規則等、日本の少年~高校までの野球の異常性をこれでもかと具体的に言語化されています。
監督は絶対的な存在であること、寄付という名の監督への金銭的な支援、選手の学年で決まる保護者の上下関係、等々。例を挙げるとキリがありません。
また、関東人の菜々子にとっては、「半歩近い」関西の距離感もストレスに感じてしまいます。

この「半歩近い」がしっくりきすぎて、僕も関西人の特徴を人に説明するときによく使っています。
前半は、そんな日本の野球教育の異常性やうまくいかない状況といった、じめじめしたストーリーで、この先どうなるのかな?ととても不安になりながら読みました。
特に、バッドエンドのような導入もあり、読み進めるのが辛かったです。
※その導入部分を先に読んでいるからこそ、最高に面白いのですけどね!
でも後半からは前半のじめじめした展開とは対照的に、尻上がりに面白くなっていきます。
かみ合っていく歯車と爽快な展開は、どんどん「先を読みたい!結末はどうなるんだ!」という気持ちにさせてくれます。
ぜひ後半まで読んでください。絶対に面白いから!
子を持つ親だけじゃなく、野球が好きな人もそうでない人も、部活を頑張っていた人もそうでない人も、いろんな人におススメできる作品です。
男の子のお母さんで良かったね!
冒頭の一文からの上のこのセリフ。物語を読んでいると、ジーンとくるものがありますよ。
アリアドネの声/井上真偽/幻冬舎
Kindle Unlimited
主人公はかつて事故で兄をなくした、会社員の高木。
その経験から災害救助ドローンを扱う会社に就職し、ドローンの操縦者兼教官として働きます。
主人公たちは、「WANOKUNI」という先鋭的な街のイベントに出席します。
この街の大半は地下に作られています。
商行施設やオフィス、インフラ設備などは地下にあり、地上には個人の住宅や教育施設等の最低限の設備が残さされているだけ。
そのイベントの舞台に登壇したのは、
「見えない、聞こえない、話せない。」の三重障害を持つ中川博美。
“令和のヘレン・ケラー”と呼ばれる彼女はとても前向きで、三重障害をものともしていません。
そんなイベントの最中、大きな地震が発生。
あろうことかその彼女が地下深くに閉じ込められてしまいます。
”見えない、聞こえない、話せない”
そんな要救助者をどのように救うのか。
主人公と消防隊の合同チームは、ドローンを使用した救助作戦を決行します。
一方、彼女はたった一人取り残されたにもかかわらず、とても冷静に行動しています。
何も見えない、急に水に落ちる、何かにぶつかる。
僕らのように目も見え耳も聞こえる人からしたらパニックになるような状況でも、彼女にとっては日常と大きく変わらない。
そんなことを考えさせてくれると同時に、そんな状況でもへこたれずに生活している彼女のような人たちを心から尊敬します。
一分一秒を争う緊迫した状況で、とある疑惑を感じながら行われるドローンによる救助活動。
そのとある疑惑により、救助活動の途中にもかかわらず作中のネット上では心無い不特定多数の誹謗中傷や憶測が飛び交います。
真実や本人の意向なんてなにも考慮されず、世論やネット上の声の大きな意見で、大きく変わってしまう恐怖も感じられます。
ぜひ最後まで読んでみてください。
最後の数ページで、真実がわかります。
真実はもっとアナログで、泥臭い。
ゴリラ裁判の日/須藤古都離/講談社
図書館より貸出
手話を操り言語を理解するゴリラのローズは、動物園で柵から落ちてしまった人間の子どもに近づいた夫ゴリラが銃殺された件について、動物園を相手に訴訟を起こします。
ゴリラは人間の子ども程度の知能を持ち、手話を理解するという実際のケースも聞いたことがありますが、本作品のように完全に人間と同程度の知能があるのでしょうか?
真実はゴリラにしかわかりません。
もしゴリラがそんな知能を本当に持っていたとしたら、これまでの「人間」と「動物」の線引きが根本から覆されてしまうような、そんな衝撃的な内容でした。
ローズはジャングルに生まれますが、ゴリラの研究者の近くで研究されながら生活することで、手話を覚えます。
彼女は人間の話す言語を理解し、手話で自身の意思を完璧に伝え、TVを観て楽しみ、おしゃれなゴリラサイズの服を着て、人間の友達もいます。
自分の手話を読み取って音声に変換してくれる特別なグローブを使うようになってからは、完全に人間とコミュニケーションが可能な状態となります。
人間と同程度の知能を持つが故に、大好きなジャングルの生活に違和感や自然の掟へのやりきれない感覚を持つようになります。
一方で、人間社会では唯一の「人語を理解する動物」として奇異の目で見られます。
彼女はゴリラだけど普通のゴリラでない。
人の言葉を理解し、手話で話せるけど、人間じゃない。
人間も動物も一緒。わかり合える人もいればそうじゃない人もいる。
どこから、何ができれば人間なのか。
言葉を理解するのが人間なのか、なら言葉を理解しない人間は人間じゃないのか。
言葉を理解する動物は人間ではないのか。
人間とは、動物とは何か。
私はゴリラではない。私は人間でもない。ゴリラと人間の合間で彷徨う何かだ。
ジェリーフィッシュは凍らない/市川憂人/東京創元社
図書館より貸出
第26回鮎川哲也賞受賞作。
21世紀版「そして誰もいなくなった」とも評価される本作。
時は1980年代。特殊な技術で開発された小型飛行船“ジェリーフィッシュ”。
そんなジェリーフィッシュの試験飛行中に起こった連続殺人事件。
連続殺人の真相を解明するため、警察官であるマリアと漣のコンビが奔走します。
ジェリーフィッシュは、飛行試験中に険しい雪山に着陸し身動きが取れなくなってしまいます。
救助を待つメンバーたちですが、一人また一人と殺されていってしまいます。
険しい雪山というクローズドサークルの状況で、誰がどのようにしてメンバーを殺したのか、犯人はメンバーの誰かなのか、それとも外部から来た者なのか。
マリアと漣が事件を捜査する過程で、徐々に浮かんでくる真相やヒント、そしてさらに深まる謎や矛盾。
いかにしてその事実に気づかせないか。
やはり叙述トリックは面白いし難しい。マリアと漣のコンビが読んでいて楽しかったです!
そして誰もいなくなった/アガサ・クリスティー/クリスティー文庫
図書館より貸し出し
ようやく読めたクローズドサークルミステリーの傑作。
クローズドサークルミステリーの元祖とも言われる本作品。
読んでみると納得。この作品が後世に与えた影響はとてつもなさそうですね。
本作品は1939年とほぼ1世紀前の作品ながら、古臭さはほぼ感じませんでした。
現代のクローズドサークルミステリーでも携帯電話や移動(脱出手段)が封じられているケースは多いです。
そうすると、結局アナログだったり原始的な手段だったりに頼らざるを得ないので、現代風な携帯電話や脱出手段がない本作も違和感なく読むことができたのかもしれません。
さて、本作品の舞台はイギリスの沖合いにある兵隊島。
その島に集められた年齢も性別も職業も異なる10人の男女には、とある共通点がありました。
島に閉じ込められてしまった彼らには、島からの脱出手段も島外への連絡手段もありません。そんな中、童謡「十人の小さな兵隊さん」の歌詞になぞられて、1人また1人と殺されていきます。
メンバーの中に犯人がいるのか、それとも隠れる場所のない孤島の中に他の誰かかいるのか。。皆、疑心暗鬼になりながらも生き残るために協力していきます。
クローズドサークルものの醍醐味は、やはり内部に犯人がいるのか、外部の者の犯行なのかが最後までわからないこと。
また、閉じられた状況でどのように犯行をするかを推理しながら真相に向かうことができる点ですね。

残念ながら、推理しても犯人を当てた経験は僕にはないのですが。。。
エピローグでの犯人の独白も面白いです。
本作に限らず、作中で真相が解明されないケースは、余韻を残す感じでいいですね。
読者が「自分は、犯人や詳細を知っているんだぜ」という優越感を感じることができます。
十角館の殺人/綾辻行人/講談社文庫
購入本
この時期はクローズドサークルにハマっていたのでしょう。
「ジェリーフィッシュは凍らない」、「そして誰もいなくなった」からのクローズドサークル3連続選出です。
よくX(旧Twitter)でも見かける作品。
クローズドサークルものの傑作とか、衝撃の展開。
などのコメントはよく見ていましたが、「どんなもんじゃい」と思って読み始めました。
結果、あの一行で衝撃を受けました。すみませんでした。
孤島にある「十角館」に集められたミステリー好きの大学生たち。
彼らにはアガサやヴァン、エラリイなど、実在するミステリーの巨匠たちの名前がニックネームとして付けられ、本人たちもそれで呼び合っています。
(いつも思うんですけど、みんななんでこんな辺鄙な場所にいくんでしょうね。まあ、意図しない場合もありますが。)
クローズドサークルものの宿命というか様式美というか、脱出手段のない孤島で、徐々に殺されていくメンバーたち。
皆疑心暗鬼になりながらも真相へ近づいていき、そして。。。
本作は上でも紹介した「そして誰もいなくなった/アガサ・クリスティー/クリスティー文庫」へのリスペクトが最大限に感じられながらも、新たな切り口でその連続殺人を実現しています。
物語は、孤島と本土が同じ時系列で、章毎に交互にシーンを変えながら進みます。
島では恐ろしい連続殺人が起こる一方、本土では奇妙な手紙の真相を探る調査が進みます。
そして徐々に情報が集まり、真相が判明します。
情報が集まり真相に近づきつつも、結局犯人は誰なんだろうとモヤモヤしてページをめくると、あの1行。
「なんだと、そんな馬鹿な。」とリアルに声が出ました。
それまでのミスリードも巧みでまったく予想していませんでした。。
そこからの種明かしパートはまさに一気読みでした。
比較的ページ数も多いですが、ダレることなく最後まで読めましたし、なにより犯人の手口がわかってからは再読したい気持ちにかられました。
これは名作といわれるのも納得。
2024年3月にhuluで実写化されたらしいですが、こんなのどうやって実写化したんだ。。
実写版も観てみたい!!

huluは以下バナーから登録できますよ!

がんになってわかったお金と人生の本質/山崎元/朝日新聞出版
Kindle Unlimited
本作の著者は、経済評論家の故:山崎元(やまざき はじめ)氏です。
本作を執筆後、2024年に食道癌でお亡くなりになられています。
山崎氏を知ったきっかけは、
「難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!(山崎元/大橋弘祐/文響社)」という本です。
それまでのお金関係の本とは違い、歯に衣着せぬ物言いですが具体例かつ定量的なケーススタディをもとに説得力のある説明に衝撃を受けたのが、山崎氏に興味を持ったきっかけです。
山崎氏の著書を読んでいると、頭でっかちの学者さんでなく、ちゃんと自分と意見が異なる人が存在することを意識しかつ尊重した上で、自身のスタンスはこれだ!と主張されています。それが人を惹きつけるポイントのように感じますね。
さて、そんな山崎氏は2020年に食道癌を患われました。
癌になってからでも腐ることなく、現実を受け止め前向きに学ぶ姿勢に心を打たれました。
死ぬまでに残された時間(期待値)を想定し、そこまでに何をして何をしないべきか。
残された家族とどう向き合い、どのように「終活」するか。
なってしまったことやそれまでに発生したコスト(サンクコスト)は気にしても仕方ない。
経済評論家ですので、がん保険や入院費用などの観点はもちろんのこと、癌で抜けてしまった際のカツラやヘアスタイルにかかる費用に至るまで、とても分かりやすくまとめられています。
「がん保険は不要」という説を山崎氏はずっと主張されてきておりましたが、実際にご自身が癌患者になってから、よりその説が肉付けされたという事実。
最後まで経済評論家の魂を感じましたし、身をもって読者である僕らに伝えてくれた気がします。
本作は、著者の一人称視点で癌になった後の心構えがとてもロジカルにまとめられています。
どの情報を入手し意思決定するか、という不確実性下の意思決定は癌だけに留まりません。
作中でも著者は、「癌患者と投資初心者は似ている」と表現されています。
生きていると、時々いいことがある
この言葉がとても胸に残りました。
もっともっと山崎氏の本を読みたかったですが、大変残念です。
おそらく悔いなくご逝去されたのではと推測します。
どこでもいいからどこかへ行きたい/pha/幻冬舎
購入本
前から書店で見かけていて読んでみたかった本。せっかく旅に行くので購入してみました。
本作を執筆時点の作者は、僕と同年代の30代半ば~後半。いろいろと共感できるところも共感できないところもあり、大変楽しかったです。
本作を読む前に想像していた内容は、国内海外問わずとにかくいろんなところにフットワーク軽くいって、いろいろな経験をするというものでした。
でも実際に読んでみると、いい意味で裏切られました。
作者は高速バスが好き、青春18きっぷが好き、ビジネスホテルが好き、チェーン店が好き…etc。
同じ場所にいるのに息が詰まったら、すぐに作業場所を変えたり住む場所を変えたり。
読んでみて思いましたが、旅なんて緻密に計画立てるより、これくらい適当な方がいいんでしょうね。
ビジネスホテルに泊まることは、外で弁当食べたりお酒を飲んだりする感覚に近いということに非常に共感を得ました。
日常の中の行動を、あえて別の場所でやってみる。
確かに、いつも自室でパソコンのキーボードを叩くのではなく、自宅近くのカフェに行って作業するのは気分転換になりますね。
意味なくビジネスホテルに泊まってみたり、サウナへ行ってみたりしたくなります。
また、僕らが普段訪れることのない地域でも、そこに住んで普段の生活を送っている人がいる。そんな場所に行ったり電車の窓から景色を見たりしながら思いをはせる、そんな気持ちも大変わかります。
著書独自の(ある意味ひねくれた)視点で、つらつらと長い独り言のように語っているのがとても癖になります。
でも不快感は全く感じません。なんでもない風景や心境を言語化するのが抜群にお上手だな。と感じました。
なんでこんななんでもないこと、なんとなくする行動を的確にかつ面白く文章にできるのだろう。
高速バス一つとってもここまで語れる感性は素晴らしいですし、カフェインやアルコールについて「ドラッグと社会の共犯関係」と表現しているのがとてもしっくりきました。
と思えば、富士山について「結構でかい」って書いているのが面白い。
僕の一番好きな話は「冬とカモメとフィッシュマンズ」です。
この作品の魅力はなんとも説明がしがたいです。
一見すると、社会になじめないアラフォーのおじさんがふらふらとお金もあまり使わず行動しているだけの本です。
でも読んだ後は、サウナに行きたくなったりビジネスホテルに行きたくなったり、なんでもない駅でふらっと降りてみたり、何か普段と違う場所へ行きたくなること請け合いです。
新しいものを見たいとしても別に遠くに行く必要はない
僕はこの本に触発され、翌日サウナに行きました。気持ちよかったです。
サウナ体験記は以下記事を読んでみてください。

誰が勇者を殺したか 勇者の章/駄犬/KADOKAWA
購入本
大好きな「誰が勇者を殺したか」シリーズ 3作目です。
いわゆる日本のRPG好きは読んで後悔はない作品。
というかRPG好きは絶対読んでほしい。
今回は「勇者の章」です。
まだまだ旅を始めたばかりの勇者アレス一行。
魔物や魔人に苦戦したりパーティ間の連携もうまくいっていなかったり。
そんなアレス達は、旅先で訪れたリュドニア国で、リュドニアの勇者:カルロス王子と出会います。
カルロス王子は魔王を倒す旅へ出ることを諦め、自国リュドニアを守る「勇者」として戦います。
そんな中、リュドニア国内の「内通者」を探すため、アレスはカルロス王子と共に行動することに。
アレスはカルロス王子から「勇者」たるもののあるべき姿を学びます。
序盤でカルロス王子の妹であるエレナ姫から「リュドニアの王子が殺された」という情報が出ますので、カルロス王子がいかに戦い死んでいったのか。という真相を探るのが本作の主な目的となります。
3作目にして初めて、勇者アレスのパーティが旅をし戦う描写が詳細に書かれている気がします。
リュドニアの勇者:カルロス王子にスポットライトを当てていますが、しっかりとアレスが勇者として成長しパーティのリーダーとなっていく様子もわかるので、まさに「勇者の章」なのでしょうね。
預言者に選ばれし勇者の陰には、勇者を立てるものもいれば妬むものもいるのが世の常。
本作では、「勇者」とは何かを様々な角度で教えてくれます。
勇者とは、強い精神力と勇気を持ち、味方を鼓舞し、癒し、自らも戦う。
勇者パーティのソロン、レオン、マリアがアレスによって変わり、泥臭く洗練されていくのもまたいいですね。
例えば、自らの剣技を誇るように派手な戦い方をしていたレオンが、敵を倒し自らを守る効率的な剣技へとシフトしていく様子なんかは、熟練の戦士へと成長する過程を見ているようで、読んでいてとても楽しかったです。
それまであまり有能でなかったように思えたカルロス王子の父も、実はとても深く現実的に考えていたことがわかるシーンがとても気にいっています。
この作品はとにかくメインキャラクター以外もしっかりと作り込みがされています。
自分がこれまでやってきたRPGの登場人物たちも、表に出てこなかった思いや葛藤なんかもあったんんだろうなと想像してしまいますね。
そして、3作目となってもタイトルに沿ったストーリーにしているのはさすがの一言。
3作とも面白さの順位が付けられないですね。
どの作品もいろんな「勇者」が存在することを僕たちに伝えてくれます。
今回も、「誰が勇者を殺したか」
以上、2025年上半期のベスト10冊でした。
毎月素晴らしい本に出合えることに感謝です!
おわり

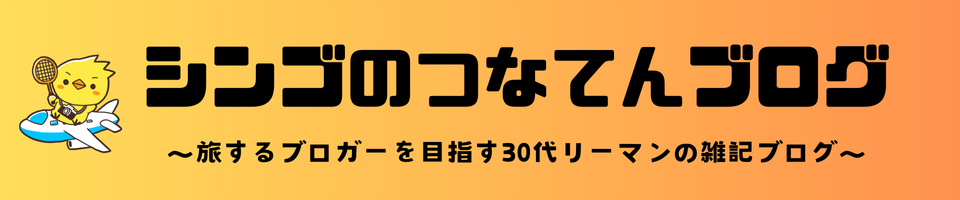






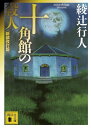






![読書しながらポイ活 [ブクスタ!]](https://shingonotsunaten.com/wp-content/uploads/2024/12/333c4b175564b1695616e8bda3a60528.jpg)